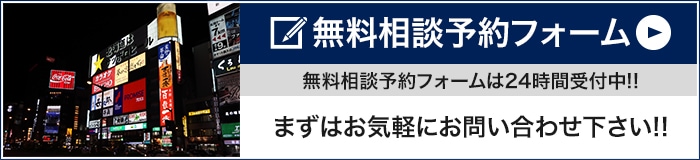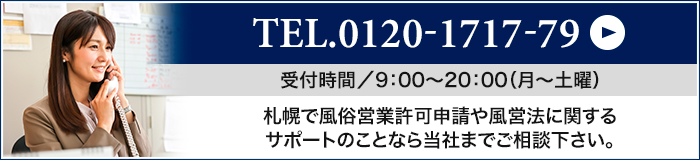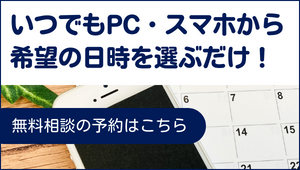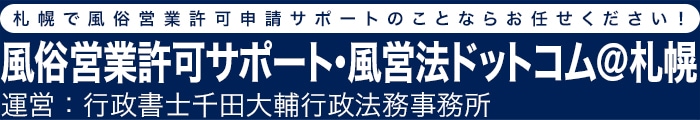居酒屋を開業するためには保健所から飲食店営業許可を取得する必要がありますが、深夜帯の営業を行う場合は、別途、深夜酒類提供飲食店の届出を行わなければなりません。ここでは、居酒屋が届出を行うべき理由や届出を行う際の注意点などについて説明していきます。
居酒屋も「深夜に酒類を提供する店」に該当する
風営法における「深夜に酒類を提供する店」として挙げられるのは、例えば以下のような業種です。なお、深夜0時以降も酒類を提供する場合を想定しています。
- 居酒屋
- バー
- スナック など
これらの業種は、風営法における「深夜酒類提供飲食店」に該当することから、店舗住所地を管轄する警察署に届出を行わなければいけません。バーやスナックが「酒類を中心に提供する業種」である一方、居酒屋は「料理と酒類を提供する業種」と性質が異なっていますが、このような場合でも、居酒屋は深夜酒類提供飲食店の届出を行うことが求められます。
「深夜酒類提供飲食店」とはどういう業態か
風営法において深夜酒類提供飲食店とは、午前0時から午前6時までの深夜帯に酒類を提供する店を指しています。警察庁が公開している「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」から抜粋し解釈していきましょう。
酒類提供飲食店営業について
飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)
※ただし、酒類を提供する店といっても、主となる提供物がご飯ものや麺類などの「主食」である場合は除かれます。
酒類を提供する店について
「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。
※どのような種類の酒類が提供されているか、どのくらいの量が提供されているかが問題ではなく、酒類を提供しているかどうか自体が重要になってくるということです。
「営業の常態として」の意味について
「営業の常態として」の解釈については、次の点に注意すること。
ア.営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。
イ.客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。
ウ.「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。
※通常「主食」と認められるようなメニューを提供することがメインであり、酒類を提供していない店は深夜酒類提供飲食店の対象外になります。また、酒類を提供していたとしても、主食の提供機会が酒類提供の機会に比べて大半である場合も、深夜酒類提供飲食店の対象外です。
深夜酒類提供飲食店の届出の流れと注意点
深夜帯に酒類を提供する居酒屋は、店舗の住所地を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店の届出」を行う必要があります。届出の流れは大きく以下の通りです。
- 必要書類の収集
- 店舗の測量と店内図面作成
- 管轄警察署への届出
- 警察による立ち入り検査
- 届出から10日後に営業開始
注意したいのが、警察による立ち入り検査時にチェックされる「店内照度」「接待の有無」です。このことについてみていきましょう。
居酒屋店内の照度は20ルクス以上
風営法では、店内の照度(明るさ)について定めがあり、深夜営業を行う場合の基準は20ルクス以上としています。
接待の有無は重要
接待行為を伴う店がとるべき1号許可(キャバクラなど)を除き、深夜営業では接待を行わないものと定められています。客に対して酌をしたり一緒にゲームなどを行ったり、あるいは特定の客との長時間にわたる談笑などが確認された場合、接待行為があると見なされますが、一般的に居酒屋のサービスは食事と酒類の提供であることから、接待については抵触しないと考えられるでしょう。
まとめ
食事と酒類を提供するごく一般的な居酒屋を開業するのであれば、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店の届出は必須になります。風営法違反となるケースの多くに接待の提供が見られやすいのですが、居酒屋であれば違反となることは考えにくいかもしれません。店内の明るさや接待の有無以外にも、店内構造などの定めがありますので、開業を検討している場合はできるだけ専門家に依頼し、法令を遵守した申請・届出を行うことができるよう努めた方がいいでしょう。当事務所では、警察OBを含むスタッフと経験豊富な行政書士が対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。